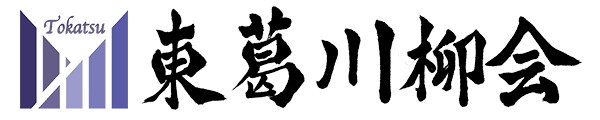三月雛祭りの頃となり、テレビでも地域の祭りが紹介されあちらこちらの雛人形を目にする機会に恵まれた。見ているうちに幼い頃、母が飾ってくれた段飾りのお雛様を思い出した。
まだ小学生になる前くらいのことだったと思う。親戚から譲り受けたものとかで、お内裏様とお姫様の最上段が、金屏風ではなくてきちんと門構えのあるお城の入口のように組み立てられており、ずいぶんと古めかしくて立派なものだった。
母は近所の友人を招いて、お赤飯やら雛菓子等で簡単なパーティーをしていた、ような記憶がある。私は大人達の賑わいを見ているだけで、何も感じてはいなかったが、母自身がとても嬉しそうで楽しそうに見えた。時折招かれた客の誰かが「〇〇ちゃん、立派なお人形でいいね」と、話かけてくれたが、コクンと頷くくらいの自分だった。
その雛人形を飾ったのは、そのとき限りで以後飾られるようなことは無く、もちろんパーティーのようなこともなかった。これが私の唯一の雛祭りの思い出。
時は流れ満十歳の誕生日を迎える頃の話。家庭の状況は変化しており、両親の離婚によって叔母の家に預けられていた私は従兄弟達と暮らす日常だった。母は住み込みで働いており普段何もしてやれないからと、この機会にプレゼントを用意しているという。しかも十歳という区切りでもあるからと、かなり豪華な品を用意している、という話を叔母が教えてくれた。「秘密だからネ」とニコニコしながら何なのかは知らせてもらえなかったが「すごいよー立派なんだよー」と盛り上げるだけ盛り上げてはくれた。
母と叔母のワクワク感は伝わるものの、何故か実感が湧かずプレゼント自体の想像もつかず、二人の大人の喜び方と私の嬉しさには、どうも温度差があるように漠然と感じていた。
昭和三十年代後半「もはや戦後は終わった」などという言われ方もされた頃だが、高度経済成長が始まりだしたとはいっても一般庶民の生活は、まだまだ大変だったろうと思う。
そんな時代、子供の誕生日プレゼントに母が選んだのは「八重垣姫」という日本人形だった。大きくて1メートル程の高さのガラスケースに赤い着物姿で大きな髪飾りを高く結った日本髪に挿し、手には兜を持って凛と立つ姫がいた。
人形を見て、大きなあ綺麗だなあ、とは思い驚きもしたけれど、嬉しいとか喜びという感情は湧いてこなかった。そこには娘の十回目の誕生日プレゼント、という名のもとに精一杯思い切った高額の買い物をしても許されるという大人の心が見えた。
そしてそれは、戦時中に子供時代を過ごした母達の雛人形はもちろん、普段の暮らしに贅沢どころか余裕さえなかった何かを埋める日本人形だったのかもしれない。
当の私は、遊べるわけでも着せ替えができるわけでもない日本人形より、当時流行りだしていて、友達が持っていたバービー人形が欲しかった。もちろん誰にも言うことは無かったけれど。