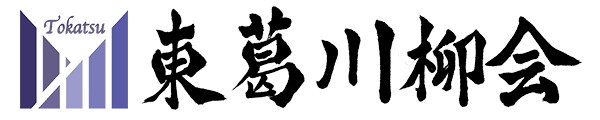巻頭言『ぬかる道』誌の魅力
こういうことは他誌では書かない。まして巻頭言に書いたりはしない(笑)。
自分の雑誌の魅力を自らアピールする。カッコイイことではない。日本的な美学にも反しよう。しかし、あえて今月号では書かせていただくことにした。理由は後述する。
人間、「慣れ」というのは恐ろしいものである。
平和が続くと、平和が当たり前だと思ってしまう。モノが溢れていると、モノを大事にしなくなってしまう。
あるいは、日本の医療保険制度。
世界に誇れる制度だということは皆さんご承知の通り。国民皆保険の制度を採っている国の方が珍しい。何しろ保険証一枚あれば、「いつでも」「誰でも」が必要な医療サービスを安価で受けられる。世界中から羨ましがられているというのが実際のところなのだ。
ところが、当の日本人はその恩恵をあまり意識していないようだ。便利さに「慣れ」きってしまって、プラス面よりもマイナス面の方に目が行きがちになっている。
魅力ある『ぬかる道』誌
それでは、『ぬかる道』誌の魅力を語らせて貰おう。
まずは全体
B5判の大きなサイズ。文字も大きくて見やすい。写真もふんだんに採り入れている。六月号の「増田幸一顧問祝白寿記念特別号」を見よ。お祝いの様子が手にとるように分かる。『ぬかる道』が愛される理由の一つであろう。
続いて、表紙絵
今年度は地元のユニーク画伯・野崎信一さんにお願いをした。毎号掲載の「表紙のことば」には、その背景が親しみやすく語られている。我孫子駅や地元の老舗も含めて、「わが町再発見」の気分が味わえる。八月号の手賀沼花火などはきわめてタイムリー。すこぶる好評だった。
表紙2
こちらには、全日本川柳大会や国民文化祭、東轄の大会案内などを載せている。ほかに、カルチャー教室やオススメ書籍の広告なども折に触れ掲載している。
五月号には、暮田真名著『宇宙人のためのせんりゅう入門』の広告を掲載した。暮田真名さんはまだ20代の川柳人である。書籍広告の宣伝効果は不明だが、それでも何人かからご注文があったらしい。『ぬかる道』に慣れきってしまうと大したことと思えないかもしれないが、こうした広告を掲載している川柳誌の方が珍しいのだ。
目次とその内容
見てお分かりのように、読み物が多い。
「句会の表情」に始まって、「鑑賞リレー」、「大人の交差点」、「ジュニア川柳欄」と続き、「編集風だより」に至るまで、内容満載である。どこを読んでも面白くてタメになる。個性豊かな書き手が多いのも特長の一つだ。
もう一言。文芸評論家の荒川佳洋先生には年に二度ほどご登場いただいている。現役の日本文藝家協会員が川柳誌に寄稿している例は、『ぬかる道』のほかに見当たらない(日本文藝家協会の理事長は、かの林真理子女史)。
巻頭言。その志の高さと話題の豊富さに各界からお褒めを頂戴しているが、まぁ詳述は避けておこう。
必要なのは人とお金
印刷物を定期的に発行するには、第一に人手が要る。
毎月の句会報
句会が終われば、入力作業が待っている。入選句は実物の句箋と一枚一枚照合され、校正に回される。校正は何人もの目でチェックする体制を取っている。
ことほど左様に、『ぬかる道』誌は多くの幹事やお仲間の手を煩わせているのだ。この場をお借りして改めて御礼申し上げる。本誌の訂正記事が驚くほど少ないのは、こうしたスタッフの皆さんの努力の賜物なのである。
雑誌が出来上がれば、今度は発送。会員名簿の整理は永見忠士幹事長が担っている。代表や会計部長と連絡を取りながら名簿を毎月チェックするのだ。神経を使う。
いざ発送となれば、句会場から300部以上の『ぬかる道』を抱えて郵便局に持ち込む。第三種郵便物に関わる必要な手続きを取りながら。永見幹事長には頭が下がる。
……これ以上は書くまい。書かなくても賢明な読者ならお分かりいただけるに違いない。水面下の大変さが。
冒頭「慣れ」の恐ろしさを指摘した。「目に見えない作業や努力」について主としてここまで書かせていただいた。
目に見える部分については、見ての通りだ。毎月の句会場での仕事ぶりが良い例であろう。句会時に於けるスタッフの動きや仕事ぶりについては、皆さん目にしておられるので巻頭言では触れなかった。あえて言及しなかった。
他方、気がつかないのは、目に見えない苦労や水面下の努力の方だ。こうして巻頭言に書いたのには、この機会に陰の努力に理解を深めていただきたかったからである。
『ぬかる道』危機突破基金をお願いした背景には、こうした事情がある。止むにやまれぬ事情である。組織を維持することと、句会を楽しんでいただくこと。これを何とか両立させたい。スタッフ一同、頑張っておられるので。
両立をさせるには、人とお金が必要になる。全く文学的ではない(!)話で恐縮だが、『ぬかる道』危機突破基金にご応募いただきたい。よろしくお願い致します。
添削教室の一時休止について
さてさて、『ぬかる道』九月号28ページをご覧にいただいたであろうか。「川柳再考Before&After」(添削コーナー)の募集が先月号で終了した。
後任を探したが、九月現在ふさわしい人物が見つかっていない。やむを得ず、いったんこのコーナーは休止とさせていただいた。誠に申し訳ない。
添削というのも陰の仕事である。一つひとつの作品と向き合って句意を推し量り、その上で添削句の提案をしていくのだ。えらく根気の要る作業でもある。加藤当白さんには現役の忙しさにもめげず、五年もの長きにわたってご指導いただいた。「勉強になる」とも言っていただいた。改めて厚く御礼申し上げたい。有り難うございました。
再開に向けて執筆者を探している。自薦他薦可。代表までお知らせいただきけると有り難い。
『ぬかる道』は今岐路に立っている。「低負担」で「高福祉」のサービスをこのまま提供出来る状況ではない。
では、「高負担」で「高福祉」の道を目指すべきか、それとも「低負担」のままで「高福祉」はあきらめて貰うのか、そのあたりの方向を検討中だ。我と思わん方は、方向性の議論に加わってほしい。これまた自薦他薦可だ。
文学に程遠いお金の話。時としてトップはこういうことも書かねばならない。