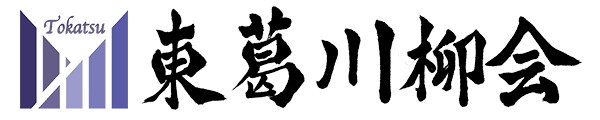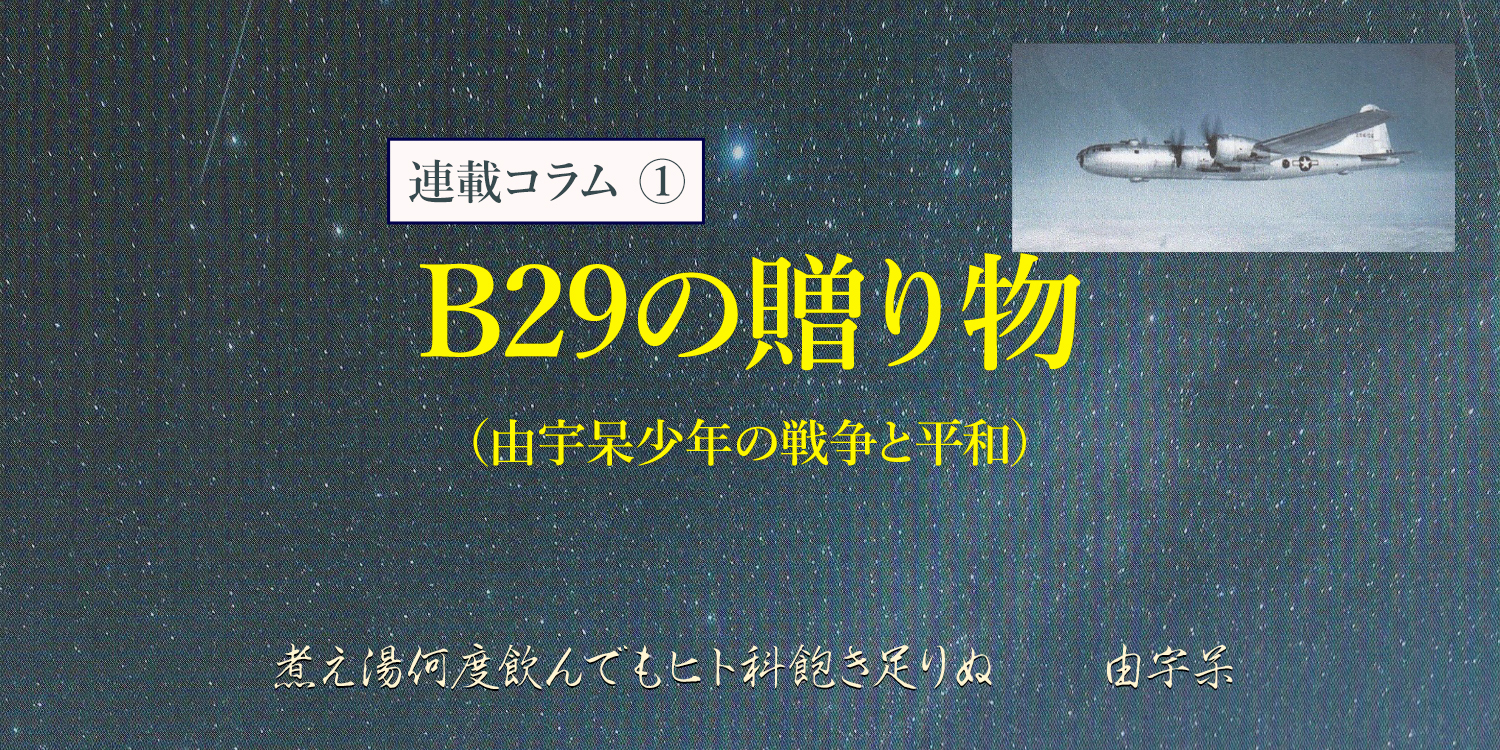初めて見上げた星空
昭和20年8月1日、午後8時、昼間から出たり消えたりしていた空襲警報が、いよいよ本物の空襲警報となって、庭先に作られた防空壕へ、否応無しに放り込まれた。防空壕からでも聞こえるように、ボリューム一杯に上げた家の中のラジオからは九時のニュースが「東海軍管区情報、東海軍管区情報、敵B29六機編隊、若狭湾上空から侵入、福井方面へ向う模様………」とガナリ立てている。防空壕の入り口から身を乗り出した由宇呆少年は、灯火管制下の夜空などとんと見上げたことがなく、始めて見る満天の星、特に天の川に徹底的に見とれていた。
由宇呆少年は、時に小学校一年生(正しくは富山市立奥田國民学校)、父は前年35歳で再招集、その時は北京の司令部勤務、通信隊だった。したがって少年は母、伯父夫婦と二軒長屋の借り上げ社宅に暮らしていた。
30分もした頃、所々に瞬く星があるのに気付いた。そして暫くして、その星がほんの少しずつ動いているのに気付いた。目を凝らすと、かなりの星が動いていた。伯父に聞くと、じっと見ていたが、暫くして「あれは敵機かもしれない。」と言った。敵機にしては爆音が聞こえない。ただ、大人たちの重苦しい気配が、ただ事ではなさそうだと、少年の呑気な頭にも解ってきた。
グラマンに撃たれる
富山市の昭和20年6月某日
話は前回よりほんの少し遡る。学校へ入学してみると、ある種の緊張感があった。前の幼稚園時代とまるで違うのである。長男で一人っ子、惣領の甚六的なひらめきしか出来なかった由宇呆少年も、入学した時の母親の言い付け「空襲警報は勿論、警戒警報でも出たら、すぐ家に帰ってくること。常に住所、氏名、年齢、本籍地、血液型を書いた布を胸につけた服を着ること。学校以外では、母親、又は伯母と一緒に行動すること。母、伯母が死んだり、家が焼けりしたら、(父親の勤務していた)会社へ行くこと。」を、しっかり覚えて実行することを、再三言われた。実際に、人の死んだ場合などに出会ったことも無かったし、実感はなかったが、あまりにも母が熱心に言うので、もし万一の時は、近所に笑われないようにしようと、心に決めていた。
6月のある日、警戒警報が出て、一年生はすぐに家に帰れ、という命令で、近所の同級生と急いでいたら、突然「キーーン」という音とともに、「ダダダダ…………」。俗にいう機銃掃射である。だいぶ離れた方で土煙が上っていたので、我々を狙った訳ではなさそうだが、怖いもの見たさに顔を上げると、翼の根元から折れたグラマン艦上攻撃機、マークは何時も絵に描く日の丸でなくて、☆型だった。始めて間直に見た戦闘機である。ゼロ戦だって実際に見たことなど無いのに。幸い、けが人は出なかったので良かったが。
山本由宇呆氏は現在87歳(昭和13年生まれ)、「我々より年長である方々にとっては、同様な体験があるはずで、決して特別な体験とは思っていない。ただ思い出して頂くもよし、それ以下の年代の方々には、そんなこともあったんだと、認識を新たにして頂ければ嬉しい。」とコメントされています。