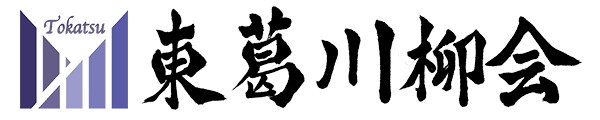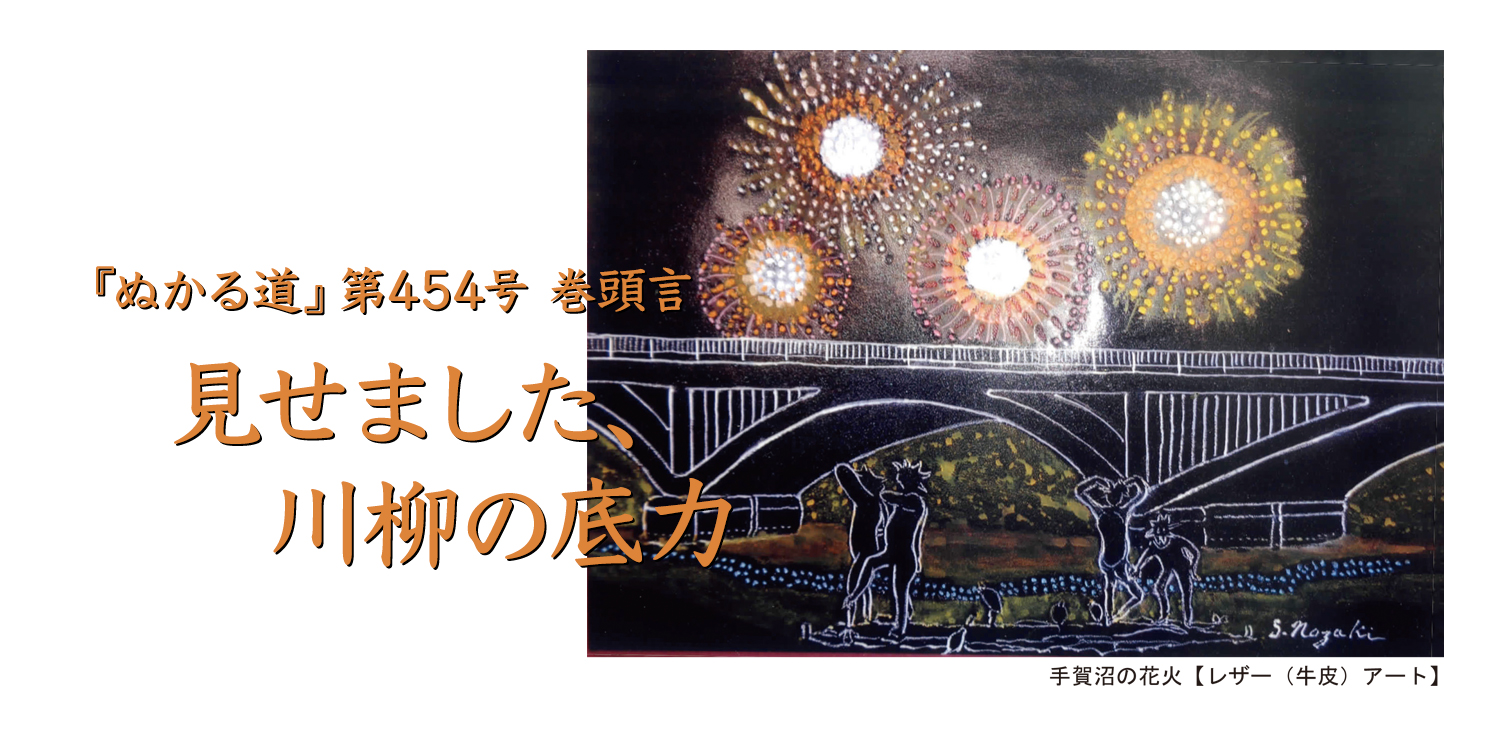巻頭言『見せました、川柳の底力』
見せました・見せました、「川柳の力」を。魅せてくれましたねえ、「川柳の底力」を。
6月22日(日)第48回全日本川柳2025年神戸大会の成功を、皆さまとともに喜び合いましょう。赤井花城実行委員長・矢沢和女副実行委員長・樋口祐子事務局長をはじめとする、スタッフの皆さんに改めて御礼を申し上げます。有り難うございました。お疲れさまでした。
「案ずるより産むが易し」
じつは小生、当日まではいろいろ気を揉んでいた(ココから文体を変える)。当初、全日本川柳協会に集まってきたのは、どちらかと言えばマイナスの情報ばかり。心配になった。大丈夫だろうか?、と不安にもなってきた。事務局員が実行委員会に何度も出向くという、異例の対応も取ってきた。舞台裏を明かせば、そうだったのだ。
しかし、いざフタを開けてみたら大盛会。しかも大成功。よかった。本当によかった!「案ずるより産むが易し」ということわざを思い浮かべたほどだった。
考えてみれば、神戸には大吟社が二つもある。日本で十本の指にも入ろうという川柳結社が二つもあるのだ。その神戸で大会が成功しないはずがない。自身の心配性を反省しつつ、そう振り返る今日この頃ではある。
6月22日(日)、神戸文化ホール・中ホールに集まったのは560 名の柳友。参加者は予想をはるかに上回った。
事前投句者、1523名。ジュニア投句者は2770名の多きに及んだ。有り難う。
付け加えれば、ジュニア川柳の講評が好評(!)だった。表彰式の舞台に立ったのは二次選者のお一人・仙波草苑さん(愛媛県)。滑舌がよい。明る<丁寧な口調。会場の皆さんには分かりやすく、入賞者の皆さんへは温かい視線を投げかけながら語りかけていた。じつに、お見事!
そうそう、懇親会も大好評だった。こちらも予想以上に盛り上がった(だが、この内容は割愛。ザンネン)。
全国大会での懇親会は、じつに六年ぶりの開催であった。これまでは「前夜祭」だった。神戸では、当日夕刻からの懇親会へと趣向を変えた。パーティーの様子は「江畑哲男熱血川柳ブログ」(7/6付け)ほかをご参照願おう(懇親宴の参加者は約130 名)。
新聞社が取材に来た「白寿記念句会」
さて、わが東葛川柳会の方に話題を移そうか。6月28日(土)、「増田幸一顧問祝白寿東葛川柳会六月記念句会」が賑々しく開催された。出席者は、ご来賓や取材記者、ご家族等を含めると80名ほどになった。コロナ禍以降、久々に楽しい楽しい集まりとなった。
明るい話題で、皆さんに喜んでいたいただいた記念句会&祝宴。この様子は今月号の『ぬかる道』にてご堪能いただきたい。そう考えて、今月号の『ぬかる道』は特集号とさせていただいている。じっくりお読みいただこう。
写真もレポートもたくさん配置した。一部重複するかもしれないが、皆さんの知らない側面を巻頭言では記す。
- ホンモノにこだわった。その好い例が和菓子の「練りきり」。縁起物の鶴と亀をあしらったデザイン。老舗のふくしま屋さん(柏市)から当日取り寄せた。美味だった!
- 豪華な選者を揃えた。「大会」と謳ってはいなかったが、大会並みの選者先生にお出で願った
- ご来賓も幸一顧問にゆかりのある方々にご来臨を乞うた。柏市文化連盟の鈴木牌勝会長、阿部俊昭県議会議員。いずれも心のこもったご祝辞を頂戴した。感謝。
- 驚いたのは阿部県議ご持参の横幕である。ナント、この日のための手作りをして下さったという。選挙戦直前のお忙しい中、夜なべ(?)に近い労作であったらしい。
- 新聞記者も取材に来てくれた。コンセプトは、「健康長寿」「白寿の現役川柳作家」である。とかく少子高齢化というテーマでは、元気の出ない情報が多い中にあって、前向きな記事にまとめてくれた。
- 小生の挨拶も好評(?)だった。「人生百年時代」。長寿も大切だが、それ以上に重視したい事柄がある。「命の重み」である。大事な大事な命をどう輝かせるか?秦の始皇帝が「不老不死」の薬を所望し、東方の海をはるばる越えて蓬莱山にやってきた。いわゆる「徐福伝説」にも触れながら、この点を強調させていただいた。
- やっぱり一番よかったのが、増田幸一顧問ご本人の御礼の言葉であろう。「川柳のおかげ」「皆さんのおかげ」を、何度何度も強調しておられた。
……かくして、記念句会も祝宴も皆さんの笑顔・笑顔で締め括られた(祝宴エピソードは割愛。ゴメンナサイ)。
夢と現実の両にらみ
もちろん、よい話ばかりとはいかぬ。ご存じのように、吟社を経営するというのは大変な時代になっている。
会計担当の山崎智幹事からは、「幹事会でも話が出ましたが、改善策を真剣に進めないと早晩首が回らなくなります」旨の忠告を頂戴している。かと言って、いきなり誌代値上げには踏み切りにくい。悩ましいところだ。
まずは現状を訴えて参りたい。その上で、『ぬかる道』危機突破基金募集をかけていく。そう考えている。具体化の折には、皆さまのご協力をぜひぜひお願いしたい。
さてさて、締めは読書ノートだ。久々の紹介になる。
『なぜハーバードは虎屋に学ぶのか』(佐藤智恵、中公新書ラクレ)。『不適切な昭和』(葛城明彦、中公新書ラクレ)。両著ともリクツ抜きに面白い。
前者は、ビジネスの話。世界最高の知性が集まるハーバード大学経営大学院で一番人気の研修先は、日本なのである。日本の長寿企業の「長寿」たる理由も教わった。
後者もまた面白かった。おそらく今年のベストセラーになるに違いない。昭和時代の景色を生き生きと楽しく再現している。「そうそう、あったあった」と共感すること間違いない。活字を愛する昭和世代必読の一著と信ずる。
今年も猛暑だ。夏こそ読書でこの猛暑を乗り切ろう!