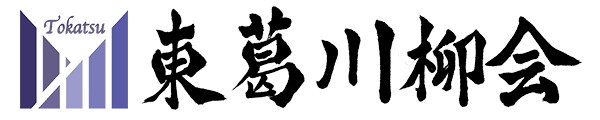半世紀以上も昔の英国で、友人に誘われてセント・オールバンスと言う町を訪れたことがありました。その町は、ロンドンから北へ20 数キロの史跡の町です。
ローマ時代の街道の遺跡が残るこの町は、ロンドンのターミナル駅セント・パンクラスから列車で30分ほどの距離にあり、今ではロンドンヘ通勤する人々のベット・タウンとも言える場所です。
そのシティの名の由来は、4世紀頃キリスト教の殉教者オールバンスが斬首された土地で、人々がオールバンスの死を悼んで修道院や聖堂を建てたそうです。
また15世紀のバラ戦争では、ヨーク家とランカスター家が交戦した場所でもあります。
この殉教者ゆかりのセント・オールバンス大聖堂を訪問した時は、日曜日の午前中で、ミサの厳かな聖歌が聴こえていました。
大聖堂に響き渡る讃美歌は、私には全く馴染のない曲でしたが非常に美しく、一応仏教徒である私でさえも、神妙にさせるものがありました。
セント・オールバンス大聖堂の周辺を散策すると、中世の古い小さな家並みがそのまま残っている地域があり、人々が幾重にも手を加えて、数百年もの間、ずっと住み続けてきたことが分かります。
そのセント・オールバンスの壁は、「バカの壁」や「106万円の壁」とは異なり、通常私たちが知っている家の外壁を指す壁のことなのです。
友人はその家並みを指して、何か気付いたことはある?と私に訊ねました。そして古い家々の壁を見てごらんと言いました。
その中世の家並みの壁を見ると、確かにそこには、それぞれ不揃いで四角形をした模様がありました。その壁の模様は、元々は窓枠だったもので、その昔、住人たちが窓をレンガや泥で埋めて塗り潰したので、窓枠だけが残って出来た模様なのです。
そこの住人たちは、なぜ窓枠だけ残して窓を埋め込んでしまったのでしょうか。
中世の頃、このセント・オールバンスを治めた領主はどんな人物だったのか、名前をしかと聞くべきだったのですが。この土地の支配者が、何かもっと他に、住民から税金を収奪する方法はないものかと考えた末に、窓に税金を掛けることを思いついたのでした。
ひとつの窓について、幾ら税金を徴収したのかは不明ですが、それを知った住民たちは、いま以上の税金を取られたのでは堪らないと、自分が住む家の窓を埋めて塗り潰し、収奪に抵抗したのでした。
住宅の窓に税金を掛けるなんて、酷い領主がいたものだと驚くと共に、世の中には様々な物に着眼して、人々から収奪する方法を捻りだす支配者がいることに、呆れたのでした。
その当時、こんな窓に税を掛ける話は、他では聞いたことがなく、中世の英国だけのことだと思われました。
セント・オールバンスの散策から約20年後に、日本では消費税が施行されました。
私は自分の質素な食事にも、味噌・醤油・漬物に至るまで、消費税を取られる国に住むことになったのです。これは全く予期しなかった事でした。
私は確かに、21 世紀の日本に住んでいるのですが。
私の川柳です。
お手柄か取り立てる策ひねり出す